昔はママチャリで配達している人が多かったフードデリバリーですが、最近ではロードバイクで配達されている方もちらほら見かけるようになりました。
見た目からして速そうなロードバイク。
実際見た目だけではなく、ママチャリと比べると楽に速度を出すことができ、楽に配達する事ができるので、配達で使用してみたいと考えている方もいるのと思います。
でもロードバイクって高いのでは?
確かに100万円を超えるロードバイクなどありますが価格はピンキリで、この価格なら購入してもいいかもと思えるものがあるかもしれません。
こちらの記事ではこれからフードデリバリーの配達で使用したいと思っている方に、おすすめのロードバイクをご紹介していきます。

【フードデリバリー】ロードバイクとは

まずはロードバイクとはどういったものかですが、なんか速そうってイメージはありますが詳しく知らない人の方が多いと思います。
簡単に言ってしまえば舗装路を速く走るために作られた自転車で、ハンドルがくるっと曲がっているのが特徴です。
また元々はレース向けに作られていたので、長時間高速で走れるように様々な工夫が施されています。
主な点は
- タイヤが細い(地面との摩擦を減らして速く走るため)
- 下向きにくるっと曲がったドロップハンドル(前傾姿勢で空気抵抗を減らすため)
- フレームやパーツが軽い(スピードを出すためには軽さは命)
- クリートでペダルと足を固定(ペダルを踏み込むだけでなく、引き上げるときもペダルを回す力に変える)
上記だけではあまり速さは伝わりませんが、プロのロードレーサーの方は70km/hもの速度が出せ、あまり運動していない成人男性でも頑張れば30~40km/hもの速度が出せます。
30~40km/hもの速度を維持するのは大変ですが、ママチャリからロードバイクに乗り換えた場合は、まったく別の乗り物だと思ってしまうくらい速く走れます。
ロードバイクの種類
ロードバイクにも車やバイクのように色々種類があります。
人によって種類分けは多少異なるでしょうが、大体こんな感じで分類されています。
オールラウンドタイプ

基本的なロードバイクのオールラウンドタイプ。
わかりやすくオールラウンドタイプと呼んでいますが、何かに特化しているロードバイクでなければこのタイプに含まれます。
安価なものから高価なものまであり、フードデリバリーの配達で見かけるのはほとんどこのタイプです。
ヒルクライムモデル

見た目ではオールラウンドタイプと区別しずらい、ものによっては見た目では区別できないヒルクライムモデル。
「ヒルクライム」=坂道を登る事に特化しているので、オールラウンドタイプより重量が軽いものがほとんどです。
エンデュランスロード

こちらも見た目ではオールラウンドタイプと区別できませんが、オールラウンドタイプと比べ長い距離を走ることに特化しています。
長い距離を走るために振動吸収に優れていたり、通常より楽な姿勢を取りやすい・少し太めのタイヤを装着している事が多いです。
オールラウンドタイプより安定性が高いです。
エアロロード

エアロロードは空気抵抗を減らすように設計されています。
その為フレームとホイールが平らになっているのが特徴で、見た目でもエアロロードと分かりやすいです。
オールラウンドタイプと比べ高速域での走りが安定しますが価格が高いので手を出しにくく、フードデリバリーでは大きなバッグを背負っているので、せっかくの空気抵抗を減らす設計が無意味になってしまいます。
TTバイク

TTとはタイムトライアルのことで、純粋に平坦な道だけを真っすぐ速く走ることに特化したモデルです。
トライアスロンでも使用されるモデルで、速いスピードを維持して走り続けられるように重視されています。
その為ブルホーンハンドルというかなり前傾姿勢になるハンドルが使用されているので、フードデリバリーでは絶対にありえないモデルです。
シクロクロス

ロードバイクは舗装路を速く走るように作られていますが、シクロクロスはオフロードを荒れた路面でも走れるようになっています。
そのためタイヤが太くて、ブレーキが泥などで故障を起こしにくいディスクブレーキが採用されています。
またシクロクロスとは競技名で自転車を担ぐこともあるので、そのようにフレームやワイヤーの位置が設計されています。
グラベルロード

シクロクロスと同じくオフロードを走るのに適したロードバイクです。
シクロクロスと細かな違いはありますが、フードデリバリーで使用するにあたってはほとんど同じと思ってもらって結構です。
またアウトドアで自転車を楽しむ人向けで、荷物の積載能力などが通常のロードバイクより優れていますが、流石に配達員用バッグを積載はできません。
ランドナー

グラベルロードより積載能力が優れている、旅をするための自転車です。
通常のモデルに比べてスピードは出ませんが、重い荷物を載せるため頑丈に作られています。
改造すれば後方にバッグを置けるように出来ます。
ピストバイク

ピストバイクとは競輪用の自転車でブレーキがないのが特徴です。
しかしそれだと公道で走ると違反になるので、ブレーキを取り付けて公道で走れるように改良されて販売されています。
フードデリバリーの配達では変速機(ギア)がないので坂道があるエリアでは辛いですが、無駄なものがないシンプルなデザインで街乗り用のロードバイクとして好まれています。
フラットバーロード

フラットバーロードはロードバイクの特徴でもあるドロップハンドルが、クロスバイクのようにフラットです。
見た目はクロスバイクに見えますがフレームや各種パーツが違い、ハンドルをドロップハンドルにすると通常のロードバイクになります。
前傾姿勢が辛い方にはいいかもしれません。
【フードデリバリー】ロードバイクのメリット・デメリット
上記の通りロードバイクと言っても色んな種類があり、フードデリバリーの配達で使用するには様々なメリット・デメリットがあります。
ロードバイクのメリット
ママチャリの重量はおよそ15kg程度に対して、ロードバイクは10kg以下のものがほとんどで、ママチャリの半分の重量7kg台のものもあります。
軽いという事はペダルを回す力(車体を動かす力)が少なくて済むので、結果的に簡単にスピードが出せるようになっています。
タイヤが細いほど地面との摩擦が少なくなり速く走れます。
ロードバイクのデメリット
メリットでもあるタイヤが細い事ですが、細い事で雨の日ではタイヤが滑りやすく、また段差や点字ブロックなどで転倒しやすいです。
価格が安いものもあるが、やはりその分性能は劣ります。
それなりの性能の物が欲しいとなると10万円前後は出したいところ。
配達でくるっと曲がった所(ドロップハンドル)を握る事はありませんが、通常の自転車と違いブレーキと変速(ギア)の握りが違うので慣れるまで戸惑うかもしれません。
前傾姿勢になるので乗りなれていないと少し怖いと思うかもしれません。一応サドルの高さなどを調整することであまり前傾姿勢にならないようにできますが、それだとロードバイクの性能を出し切る事ができません。
【まとめ】ロードバイクのメリット・デメリット
価格によって性能は様々ですが、電動のママチャリと同等、もしくはそれ以上に少ない力でペダルを回せてスピードが出せます。
それなりの物を購入しようとなると価格はどうしても10万円程度を見てもらわないといけませんが、電動のママチャリも同程度の価格ですので、電動のママチャリの購入を考えていた方は、ロードバイクも候補に入れてみてはどうでしょうか。
価格が高いのはどうしてもという方は、型落ちのセール品などが売られていれば5万円程度で購入できる事もあります。
タイヤが細いことが不安な方は、少しスピードは落ちますがグラベルロードを購入することで問題は解決でき、ドロップハンドルのブレーキや変速は慣れるしかありませんが、慣れないようでしたらフラットバーロードという選択もあります。
前傾姿勢に関してはサドルなどを調整すれば改善できますが、ロードバイクの性能を出し切れないので出来れば前傾姿勢のままの方がいいです。
【フードデリバリー】配達で使用するロードバイクの選び方
フードデリバリーで使用するなら「オールラウンドタイプ」「エンデュランスロード」「グラベルロード」あたりがおすすめです。
雨の日も稼働される方はタイヤの太いグラベルロードがいいでしょう。
またロードバイクは通常の自転車と比べ、自分の体のサイズにあったものを選ぶことが重要です。
あとはデザインや性能であったり、財布と相談して選びましょう。
体のサイズにあったロードバイクを選ぶ
ロードバイクはフレームのサイズが合わないと、極端に前傾姿勢になったりなど怪我のリスクが高まります。
自分に合ったものを選ぶためには、ママチャリのようにフレームのサイズごとの適正身長で選ばない方がいいです。
理由としてサドルの高さやハンドルの位置など細かな調整が必要なので、できればロードバイクを取り扱っている自転車専門店などで選ぶことをおすすめします。
デザインでロードバイクを選ぶ
ロードバイクのメーカーは沢山あり、メーカーによってフレームの形が若干違ったり、メーカー特有のデザインのものがります。
有名なのはBianchiというメーカーのチェレステカラーあたりでしょう。

Bianchiのチェレステカラーは人気のモデルで、街中で一度は見かけた事があるのではないでしょうか。
他には鮮やかな青が特徴のGIOSというメーカーのジオスブルーというカラーのモデルもあります。

このように各メーカーでしかないカラーリングのものもあり、デザインでロードバイクを選ぶのも一つの手です。
財布と相談してロードバイクを選ぶ
ロードバイクの価格は型落ちセール品などで安くて5万円程度からあり、上を見ると車並みの価格で数百万円します。
たまに5万円以下のロードバイクがありますが、見た目だけロードバイクで性能はママチャリ並みの「ルック車」と呼ばれるものなので気を付けてください。
性能でロードバイクを選ぶ
性能でのロードバイクの選び方ですが、まずはフレームの材質が主にアルミ・カーボン・クロモリの3種類があります。
各材質を簡単にまとめた特徴ですが
| メリット | デメリット | |
| アルミ | 安価。 | 振動吸収性が悪い。 |
| カーボン | 重量が軽い。 | 高価。衝撃で壊れやすい。 |
| クロモリ | 衝撃に強い | 重量が重い。錆びやすい。 |
フードデリバリーの配達で使用するにはアルミがおすすめです。
カーボンフレームだと安くても20万円位はしますし、一度転倒しただけでフレームが割れてもう使い物にならないという事も十分にありえます。
次にパーツ「コンポーネント(略してコンポ)」のグレードです。
コンポとはディレイラー(変速機)にブレーキ、クランク(ペダルが付いているパーツ)・変速レバーのことを指します。
そしてロードバイクの多くは日本のSHIMANO製のパーツが使用されており、SHIMANO製でなければイタリアのCAMPAGNOLO(カンパニョーロ)というパーツが使用されています。
このコンポは自分で改造してコンポを取り換えなければほぼSHIMANO製ですので、SHIMANO製のコンポのグレードをご紹介していきます。
| SHIMANO製コンポーネントのグレード(グレードの高い順) |
| DURA-ACE(デュラエース) |
| ULTEGRA(アルテグラ) |
| 105(イチマルゴ) |
| TIAGRA(ティアグラ) |
| SORA(ソラ) |
| CLARIS(クラリス) |
| TOURNEY(ターニー) |
グレードの高いコンポほどギアの枚数が増えたり、軽量で耐久性、そして操作性が優れています。
操作性とはスムーズにギアを変更出来たり、ブレーキの制動力の事を指します。
フードデリバリーで使用するには105以下のコンポがおすすめで、105だとレースにも出れるコンポで15万円位から搭載されているロードバイクがあります。
逆にULTEGRA以上になるとがっつりレース仕様となり、価格も跳ね上がります。
最後にタイヤ・ホイールの性能です。
タイヤ・ホイールの性能は様々で、コンポと比べて単純なグレードで表すことができず、自分の走り方や走る場所によっておすすめのタイヤ・ホイールが変わってきます。
細かく分類すると長くなりますので、今回は簡単にご紹介していきます。
まずはタイヤについてですが、主にクリンチャータイヤ・チューブラータイヤ・チューブレスタイヤの3種類がありますが、初心者にはクリンチャータイヤがおすすめです。
クリンチャータイヤはタイヤとチューブが別になっているいわゆる普通のタイヤで、初期タイヤとしてほぼこのタイヤが着いています。
チューブラータイヤはタイヤとチューブが一体化しており、チューブレスタイヤはチューブがありません。
どちらも整備には知識と技術が必要であったり、初心者にはおすすめできません。
次にホイールについてですが、こちらもフレームと同じく材質の違いがあります。
材質はアルミとカーボンですが、アルミ=安い、カーボン=高い・軽いとざっくり説明するとこんな感じです。
そして材質以外にもノーマルリムとディープリムという違いもあります。
ノーマルリムがこちら。

ディープリムがこちら。

ホイールのリム部分の高さが違い、ディープリムは空気抵抗を減らしてくれますが横風に少し弱くなったり、重量が少し重くなるという欠点があります。
またあまりスピードを出さない方にとっては、ディープリムの効果をあまり感じることが出来ないでしょう。
ロードバイクに必要なもの
ロードバイクを選び終えたら、公道で走るために必要なもの、またこれはあった方がいいという物があります。
ペダル
実はロードバイクには一部エントリーモデルを除きペダルが付いていないのです。
ですのでロードバイク本体を購入したら+ペダルも購入しないといけません。
ではどうして別売りなのかというと、ロードバイクにはシューズとペダルを固定する「ビンディングペダル」が使用されています。

このビンディングペダルには「SPD」と「SPD-SL」という2つの規格があり、互換性がないのでそれぞれに合うシューズを用意しないといけません。
もしSPDのシューズを持っているのにSPD-SLのペダルが付いていたら、ペダルを変えるかシューズを変えないといけませんよね。
ただロードバイクには絶対にビンディングペダルを付けないといけない訳ではなく、ママチャリ等で使用されているシューズとペダルを固定しないペダル「フラットペダル」を取り付けることも可能です。
ビンディングペダルは最安で3000円程度から、フラットペダルは最安で1000円を切る価格から販売されています。
ビンディングシューズ・クリート(※ビンディングペダルを使用する場合)
フードデリバリーでビンディングペダル使用している方は見かけた事はないのですが、もし使用する場合は「ビンディングシューズ」と「クリート」が必要となります。
ビンディングシューズは安くて4000円程度から販売されており、ペダルの種類(SPDかSPD-SL)を間違えないように気を付けてください。
そして「クリート」とはビンディングシューズとペダルを固定するためのパーツです。
最安で1000円程度で販売されており、こちらもSPDかSPD-SLかを間違えないように購入してください。
ライト

日が沈んだ後に走行する予定があれば、ライトを取り付けて点灯させていないと道路交通法違反となります。
よくライトを点滅させている方を見かけますが、こちらも厳密に言えば道路交通法違反で、日没後に走行する場合はしっかりとライトを点灯させておきましょう。
ただライトは点灯させていればOKという訳でなく、「白色または淡黄色で夜間に前方10メートルの距離にある交通上の障害物を確認できる明るさ」で照らさなければいけません。
上記の明るさは大体300ルーメン前後の明るさを表しており、ルーメンとは光そのものが放つ光の強さで、ライトの明るさを表現する際に使用されています。
またライトの種類には乾電池式と充電式の物があり、乾電池式のものが価格が安い・明るさが弱い、充電式のものが価格が高い・明るさが強いという傾向があり、300ルーメン前後のものであれば3000円程度あれば購入できるでしょう。
空気入れ

空気入れも絶対に必要なアイテムです。
もちろん空気入れを持っていなくても公道は走れますが、ママチャリなどと違い空気を入れる頻度が高く、できれば乗る前に毎回・最低でも1週間乗ったら1回は空気を入れたいところです。
またママチャリ用の空気入れを持っている方でも、ロードバイクでは空気を入れるバルブ部分の構造が違い、また所々で無料で空気を入れれる所がありますが、大抵ロードバイクのバルブに対応していない空気入れになるので新しく購入する必要があります。
ではどの空気入れを購入すればいいのかは「仏式バルブ」に対応しているもので「空気圧のメーター」が付いているものです。
仏式バルブがロードバイクで使用されているバルブで、空気圧のメーターが必要なのは適正気圧の空気を入れないと、パンクしやすかったり乗り心地が悪くなるからです。
一応ママチャリのタイヤにも空気圧はありますが、適正気圧でなくともロードバイクほどパンクしやすかったり乗り心地が悪くなる訳ではありません。
空気圧メーター搭載で仏式バルブ対応の空気入れは、大体3000円程度から購入することが出来ます。
鍵
ロードバイクは高額で盗難されやすいので、丈夫なカギを購入した方がいいです。
カギにも色々種類がありますが、できればU字のものでなく丈夫で長いチェーン状のものがいいです。

その理由として前輪と後輪を巻き込むようにしてカギをかけたいからです。
ロードバイクにはタイヤだけで数十万するものがあり、フレームはカギで何かと繋げて取られないようにしていても、タイヤだけ盗まれてしまうというパターンもあります。
丈夫で長さのあるカギとなると大体3000~4000円程度から販売されています。
キックスタンド

外で止めるための「キックスタンド」ですが、ロードバイクには少しでも重量を軽くする・フレームへのダメージを無くすため、ほとんどのモデルでスタンドが付いていません。
またスタンドがない方がかっこよく見えるのという理由もあるでしょう。
ですので基本的にロードバイクを止める場合は何かに立てかけたり、サイクルラックがあればそこにサドルを引っかけて止めるようになります。
しかしフードデリバリーで使用する方にとってはスタンドがないと不便です。
キックスタンドは見た目や重量などをこだわらなければ1000円以下と安価に購入できます。
【フードデリバリー】ロードバイクで配達 まとめ
ロードバイクは本体以外にも色々とお金がかかりどうしても高額になってしまいます。
ただ楽にスピードを出せる事は間違いないので、長くフードデリバリーの配達を行うのであれば購入を検討してみてはどうでしょうか。
しかし10万円近くのお金となるとポンと出せる額ではないので、まずは自転車専門店などに足を運びいろんなロードバイクを見てください。
なかには試乗できるロードバイクもありますので、それから購入するか検討するものいいでしょう。
また付属品を一つ一つ揃えていくととても面倒ですが、ショップによってはロードバイク入門セットみたいな感じでまとめて売っていたりして簡単に揃えることもできます。
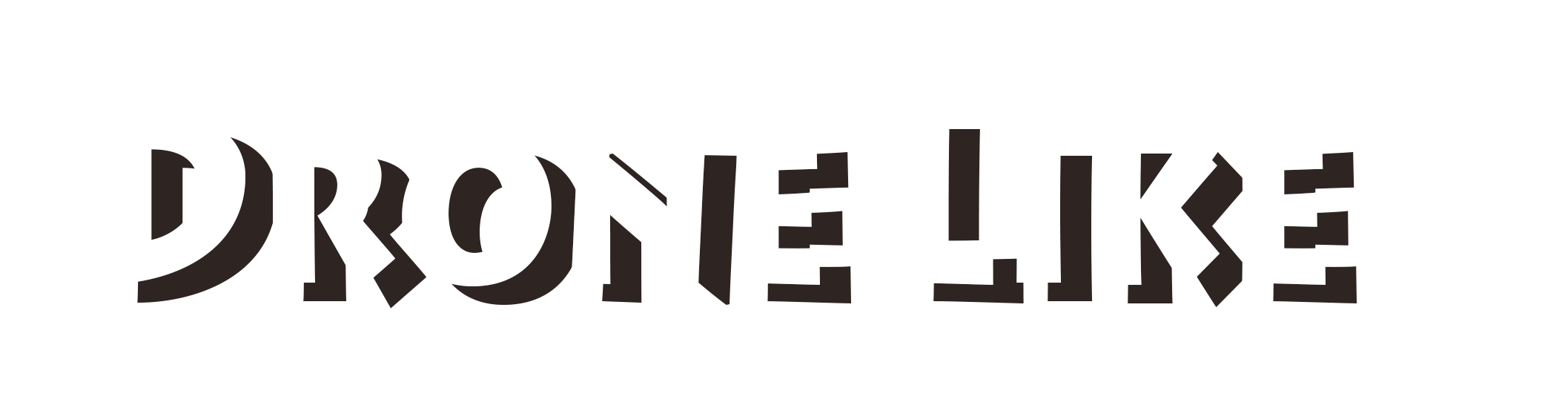









コメント